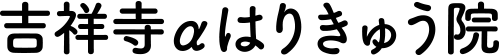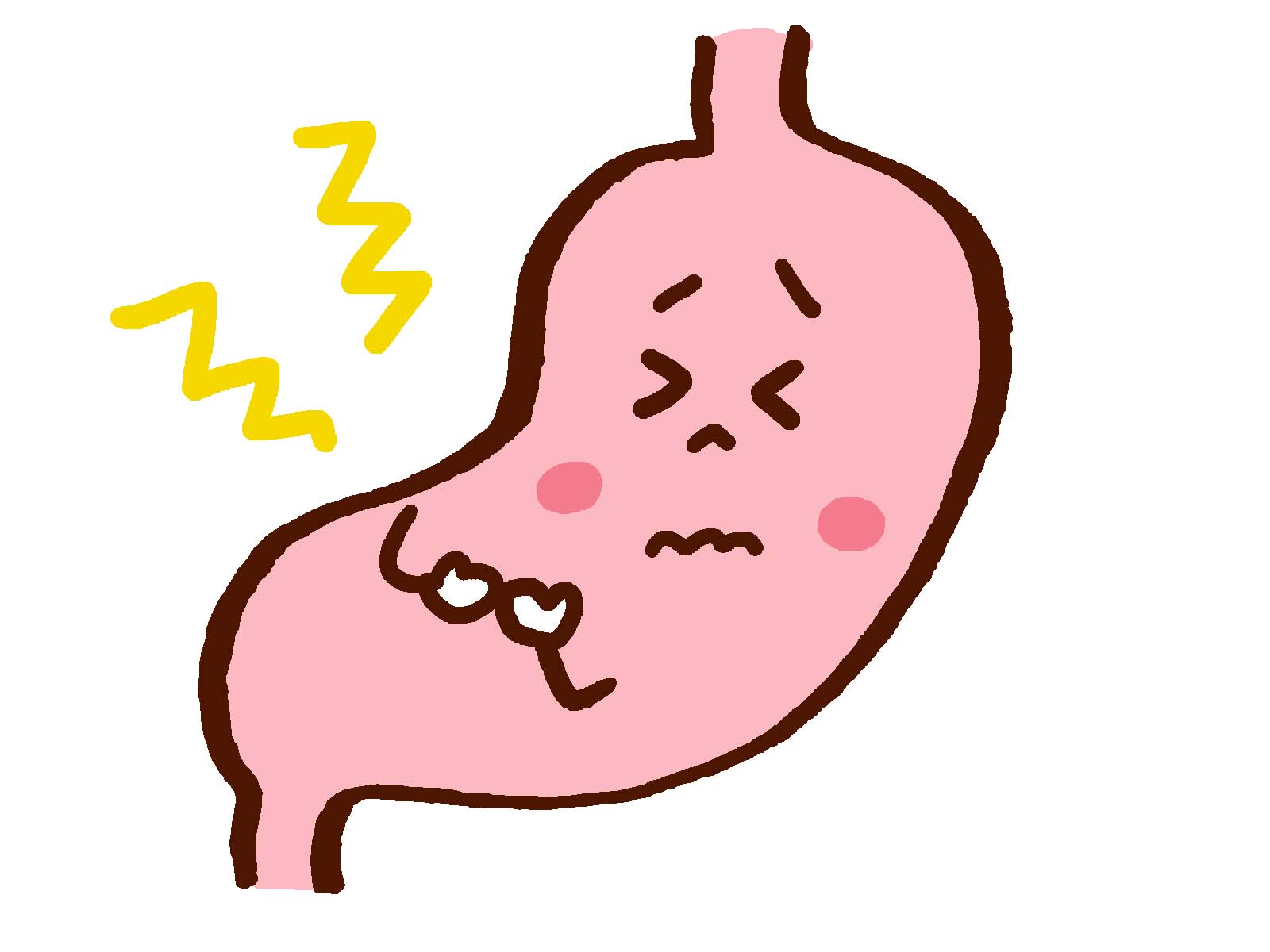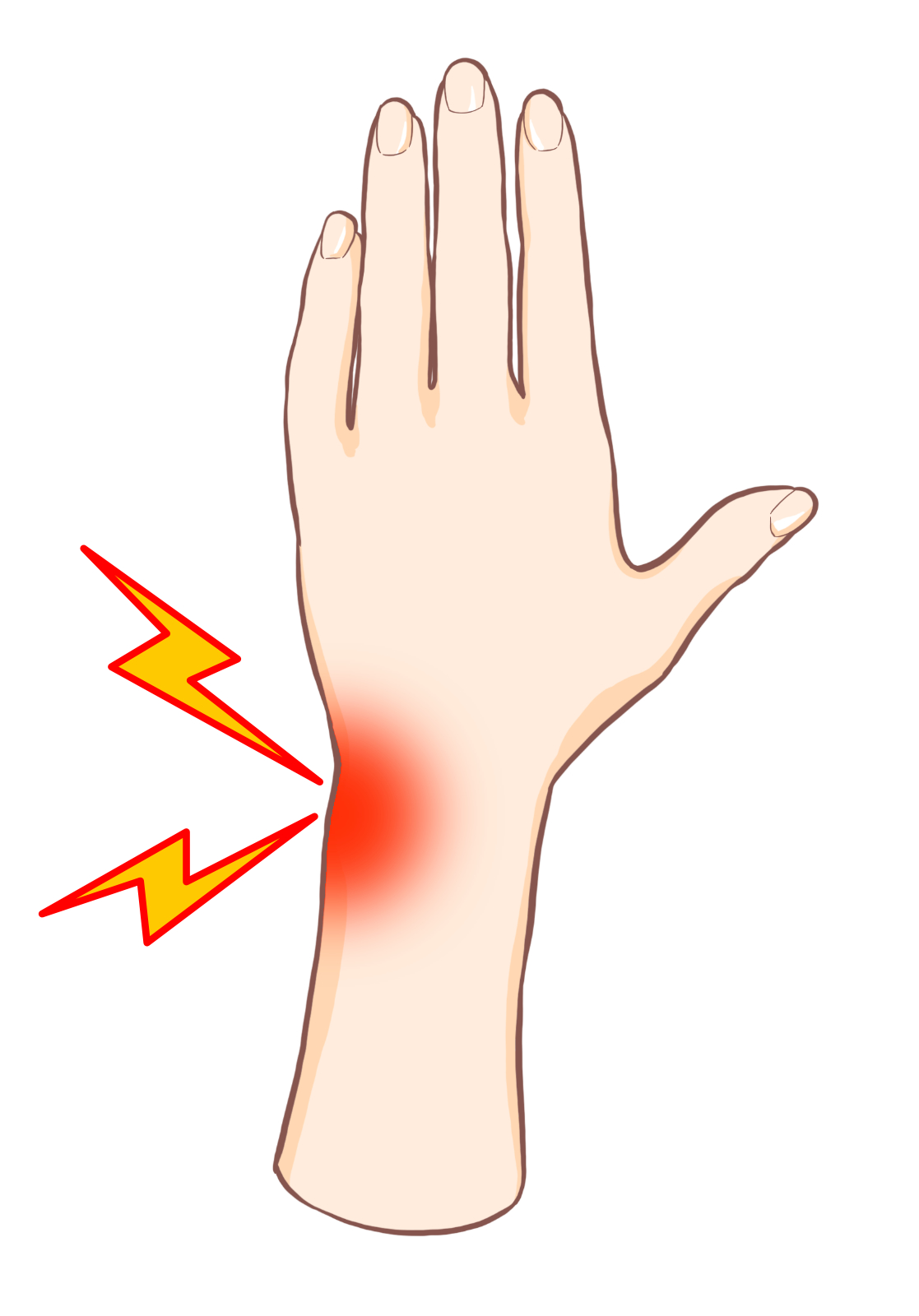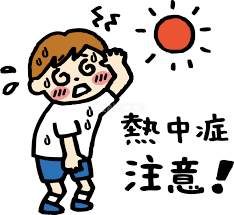お知らせ & コラム NEWS / COLUMN
辛いお腹の張り、便秘の症状には鍼灸治療を!

【便秘とは?】
便秘とは、便が大腸内に停滞し、排便の回数や量が減った状態、または便をスムーズに排出できない状態を指します。
一般的に、健康な便通は24〜48時間(1日〜2日)に1〜2回規則正しくあるのが通常です。便秘と判断されるのは、目安として3日〜数日に1回の排便になった場合が多いです。
便秘は国民の約15%が悩む一般的な症状で、男性よりも女性に多く見られます。ただし、60代後半からは男女ともに増加し、80代では男性が上回ることもあります。
便秘に加えて、排便困難、残便感、お腹の張り、腹痛、ガス溜まりなど、さまざまな不快な症状が伴うこともあります。
【あなたの便秘はどのタイプ?】
便秘は大きく分けて2つ種類があります。
「機能性便秘」
大腸自体に病気がなく、機能的な問題で起こる便秘です。症状によってさらに3つに分けられます。
1.弛緩性便秘
-
特徴: 大腸の動き(ぜん動運動)が低下し、便の通過が遅くなることで、水分が過剰に吸収され便が硬くなります。
-
多い方: 高齢者や妊婦さんなど、お腹の筋肉の力が弱まっている方に多く見られます。
-
関連症状: 肩こり、頭痛、めまい、だるさなど、自律神経の不調を伴うこともあります。
2.痙攣性便秘
-
特徴: 自律神経の乱れ(特に交感神経の過緊張)により、大腸が痙攣して便の流れが悪くなる便秘です。便秘と下痢を繰り返す「過敏性腸症候群」の一種としてもよく見られます。
-
便の状態: 排便時に腹痛を伴いやすく、便はコロコロとしたウサギの糞状になることが多いです。
-
原因: 精神的なストレスで症状が悪化しやすい傾向があります。
3.直腸性便秘
-
特徴: 便が直腸まで到達しているのに、直腸の感覚が鈍くなったり、排便に必要な筋力が低下したりして、うまく排出できない便秘です。
-
原因: 加齢による筋力低下や、便意を我慢する習慣によって排便反射が起こりにくくなることが主な原因です。
「二次性便秘」
何らかの病気が原因で起こる便秘です。これらは鍼灸治療の適用外となり、速やかに医療機関を受診する必要があります。
-
器質性便秘: 大腸がん、クローン病、潰瘍性大腸炎など、腸自体の病気が原因。
-
症候性便秘: 脳血管障害、パーキンソン病など、他の病気の症状として現れる便秘。
【東洋医学からみた便秘の原因:体質別4つのタイプ】
東洋医学では、便の排泄は大腸の「伝化機能」(消化物を便として排泄する機能)によって行われると考えます。この機能は、他の臓腑(内臓の働き)や、「気(エネルギー)」「血(血液)」「津液(体液)」といった生理物質のバランス、体の「寒熱」の偏りなど、さまざまな要因に影響されます。
大腸の伝化機能に特に影響を与える臓腑の機能としては、以下のものがあります。
-
肝(かん)の疏泄(そせつ): 気の巡りをスムーズにする働き。
-
肺(はい)の宣発(せんぱつ)・粛降(しゅくこう): 呼吸や水分代謝、気の巡りを司る働き。
-
脾(ひ)の運化(うんか): 飲食物を消化吸収し、全身に栄養を運ぶ働き。
これらのバランスが崩れることで、便秘のタイプが異なると考えられます。
-
熱秘(ねつひ):体に熱がこもる便秘
-
特徴: 辛い物の偏食などで胃腸に熱がこもり、体の潤い(津液)が不足することで排便が困難になります。
-
症状: 便が乾燥して硬い、お腹の張り、おならが多い、排便後にスッキリしない。
-
-
気秘(きひ):気の滞りによる便秘
-
特徴: ストレスや感情の乱れ(情志の失調)により「気」の巡りが滞り、肝の疏泄機能や大腸の伝化機能がうまく働かなくなることで起こります。
-
多い方: 長時間座っていることが多い方に多く見られます。
-
症状: 便意はあるのにスッキリ排便できない、げっぷが頻繁に出る、わき腹や胸の痛みなどを伴う。
-
-
虚秘(きょひ):気や血の不足による便秘
-
気虚(ききょ)による虚秘: 肺や脾の機能が低下し、大腸のぜん動運動が弱まることで起こります。
-
症状: 排便する力が出ない、疲労感やだるさ、息切れなどが見られます。
-
-
血虚(けっきょ)による虚秘: 体の「血」が不足し、腸内が潤不足になることで起こります。
-
症状: 便が硬くコロコロしている(兎糞状)、顔色にツヤがない、めまいなども見られます。
-
-
-
冷秘(れいひ):体が冷える便秘
-
特徴: 体が虚弱で、下半身の「陽気」(体を温めるエネルギー)が不足し、体の温める機能が低下することで排便が困難になります。
-
症状: 排便困難で、ときどきお腹が冷えて痛む、手足の冷えも感じやすいです。
-

【当院の鍼灸治療】
1.自律神経を整える
自律神経測定器で自律神経のバランスを測ります。
便秘の方は、交感神経が優位になっていることが多く、下痢の方は副交感神経が優位になっていることが多いです。
自律神経の状態は個人差があるため患者様に合った治療法、ツボを選択して治療を行います。
自律神経が整えられると、大腸の蠕動運動が促進され便秘が改善されていきます。
また、胃腸の調子はストレスと深い関係があります。
鍼灸治療には副交感神経を高めリラックスを促す効果があり、ストレス解消につながります。
2.胃腸を動かすツボを刺激する
便秘の鍼灸治療では胃や腸の調子を取り戻すようにします。
胃、脾、大腸などが乱れているために引き起こされているので、これらの経絡経穴を刺激することで、腸の運動を刺激していきます。これにより腸内の便の移動が促進され、便秘の緩和を図ります。
【自宅でできる便秘ケア!おすすめのツボ】
・足三里 膝のお皿の下外側から指4本分下に位置します。
腸の蠕動運動を促します。
・中髎 仙骨の上にあり、仙骨孔の上から3つ目に位置します。
骨盤神経を刺激し、下部結腸や直腸の蠕動運動を促し、排便機能を正常化させます。
【便秘改善のための生活指導~東洋医学からのアドバイス~】
・水分の過剰摂取や偏食は脾胃の働きを低下させるため、気虚または血虚を引き起こす原因になります。規則正しく栄養バランスのとれた食事をとりましょう。
・過労、睡眠不足も脾胃の働きを低下させますので、適度な休養と睡眠を心がけましょう。
・気滞は、肝の疏泄機能(イライラ)や情志の失調(落ち込みやすい)を発生させストレスを誘発させます。日常生活の中で趣味や軽い運動をするなど、ストレス発散する手段をもちましょう。

【グループ院のご紹介】
東京α鍼灸院:中目黒駅
渋谷α鍼灸院:渋谷駅
三茶はりきゅう院:三軒茶屋駅
高田馬場はりきゅう院:高田馬場駅
ご予約はこちらから
\相談だけでも大丈夫ですのでお気軽に/
はじめての方も安心の返金保証制度をご用意しております。
たった一度のご来院でも、我々の専門知識と確かな技術で
お客様のお悩みの症状に対する概念を、きっと変えられると思ってます。
是非一度お気軽にご相談ください。